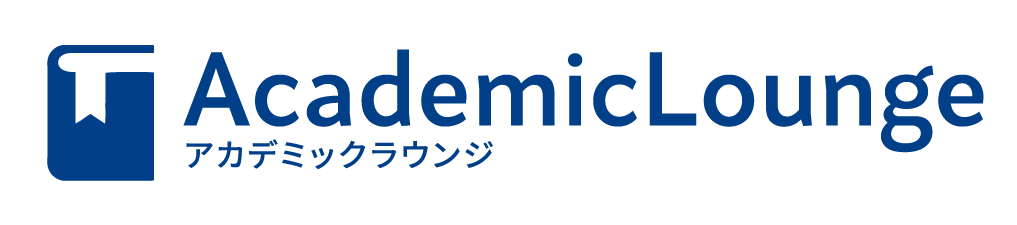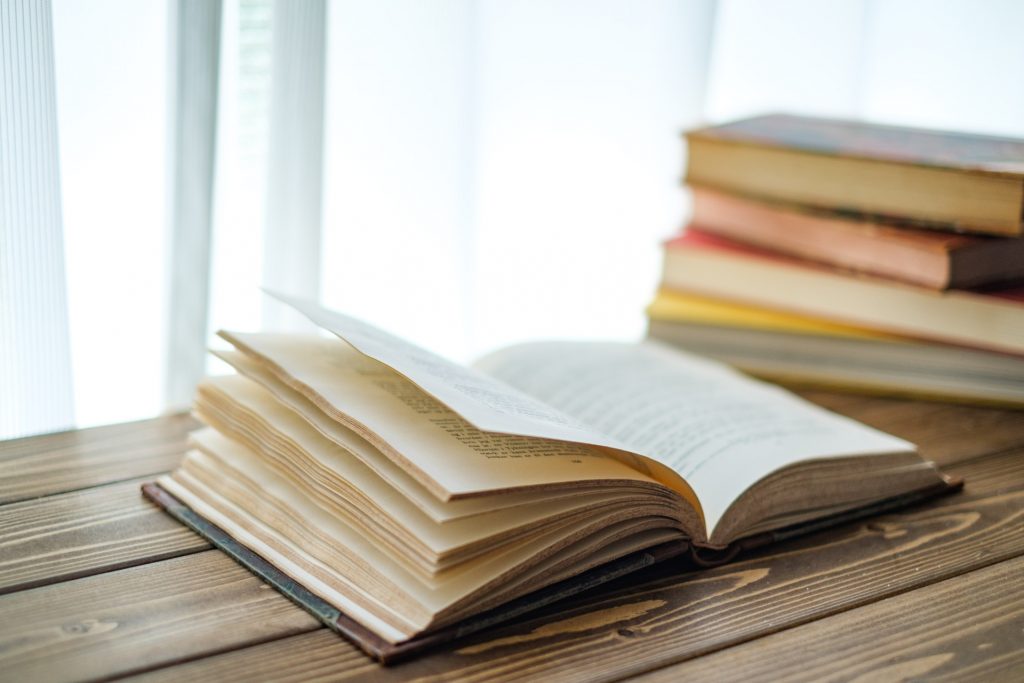研究者が教えるアカデミックライティングのコツ10選
論文やレポートでは、文章表現が硬くなったり回りくどくなったりすることが多いため、以前の記事で文章を読みやすくするためのコツを5つご紹介しました。まだご覧になっていない方は、こちらの記事からご覧ください。
今回の記事ではその第二弾として、新たに5つのコツについてご紹介したいと思います。今回参考にしたのは、以下の本です。
『社会人になったらすぐに読む文章術の本』藤吉・小川、2023年、KADOKAWA
論文やレポートなどのアカデミックライティングについて書かれた本ではありませんが、だからこそ一般的な読者の目線で読みやすい文章を書くコツがまとめられています。その中からアカデミックライティングにも当てはまるコツに注目し、前回の記事では取り上げられなかった点をまとめていきます。
「こそあど」言葉を多用しない
「こそあど」言葉とは、「この」「その」「あの」「どれ」などのように物事を抽象的に指し示す言葉です。短く表現できて便利である反面、読者には何を指しているのか分かりにくいことがあります。
元の文章
改札を出たら正面の通り(○○通り)を左に進んでください。そこを100メートルほど歩くと、左手に黒い10階建てのビルがあります。それを通り越したら左折してください。そこの左手の2軒目の建物が弊社です。
改善例
改札を出たら正面の通り(○○通り)を左に進んでください。100メートルほど歩くと、左手に黒い10階建てのビルがあります。ビルを通り越したら左折してください。左手の2軒目の建物が弊社です。
どちらの文も、上でご紹介した本からの引用です。「改善例」では不必要な指示語を削除し、必要な場合は明確に(今回の場合は「ビルを」)示しています。
科学系の論文やレポートで「こそあど」言葉が頻繁に見られるのは、研究方法を説明するときです。実験や調査の方法を順番に淡々と説明していくなかで、ついつい「その・・・」「この・・・」のように説明してしまいがちです。
もちろん著者はその指示語が何を指すのか分かって書いているのですが、実際に実験・調査をしていない読者にとっては、指示語が何を指しているのか分からない可能性もあります。読者の目線に立って、指示語を使っても問題ないかどうかよく考えながら書きましょう。
程度を表す副詞は具体的な数字に置き換える
「とても」「大変」「大きく」「少し」「ほとんど」などは「程度を表す副詞」で、論文やレポートの文章でもよく使用されます。しかし、正確さや明確さが常に求められる論文・レポートでは、そのような曖昧な表現を使用するときは十分に注意しましょう。
元の文章
実験では、溶液Aを十分に熱くなるまで加熱した。
改善例
実験では、溶液Aを90度で10分間加熱した。
元の文章
調査結果を見ると、地域Aに比べて地域Bでは人口が大きく増加した。
改善例
調査結果を見ると、地域Aに比べて地域Bでは人口が20%増加した。
「十分に」とか「大きく」と言われても、読者は「どの程度?」と思ってしまいます。程度を明確に表現できる場合は、具体的な数字を使って説明するようにしましょう。
ただし、必ずしも数字を使う必要はなく、抽象的な表現で事足りる場合もありますので、どちらが良いのか読者の立場になって考えます。
根拠を示して説得力を高める
論文・レポートで自分の主張を展開したり研究の正当性を高めたりするためには、根拠を示すことが大切です。「なぜそうしたのか」「なぜそう考えたのか」「なぜこう結論づけるのか」と、常に「なぜ」を意識しながら書くようにしましょう。根拠の示し方としては、次のような例が挙げられます。
行為の理由を示す
サンプルに含まれる水分を除くため、乾燥器を使って60度で5時間乾かした。
先行研究や参考文献を示す
〇〇の研究によると・・・だったため、今回の実験では60度で5時間乾燥させた。
カタカナ語を乱用しない
研究者や専門家が普段何気なく使っているカタカナ語には、分野外の人には理解できない言葉が多くあります。そのようなカタカナ語を多用すればするほど、論文やレポートを読んで理解できる人は限定されてしまいます。自然な日本語にできる場合はなるべく日本語に置き換えましょう。
ただし、翻訳された日本語よりカタカナ語のほうが広く浸透していたり、日本語とカタカナ語で微妙にニュアンスが異なったりする場合もあります。読者を想像しながら、最もふさわしい表現を選ぶようにしましょう。
主語と述語を対応させる(呼応表現)
論文やレポートなどの専門的な文章では一文がついつい長くなってしまいがちで、その結果、主語と述語がうまく噛み合っていない文になることがあります。
元の文
今回の実験が前回と異なるのは、サンプルに水分が含まれると化学反応が十分に進行しない可能性があるため、サンプルを事前に60度で5時間乾燥させた。
改善例
今回の実験が前回と異なるのは、サンプルに水分が含まれると化学反応が十分に進行しない可能性があるため、サンプルを事前に60度で5時間乾燥させたことだ。
元の文の主語は「異なるのは」です。「のは」の「の」は、「〜(の)こと」「〜(の)もの」を表すため、文末の述語を「〜ことだ」にすると、主語とうまく合います。
そもそもこの例文では、主語と述語が離れすぎていて意味を理解しづらいという問題があります。語順を入れ替えて、見かけ上の主語をなくすと(主語無表示文)、さらに読みやすくなります。
改善例
サンプルに水分が含まれると化学反応が十分に進行しない可能性があるため、今回の実験ではサンプルを事前に60度で5時間乾燥させた。
まとめ
以上をまとめると次のようになります。1〜5が前回の記事、6〜10が今回の記事でご紹介したものです。
- 一文一義を心がける
- 読点の位置や数を考える
- 同じ文末表現を連続させない
- 長過ぎる修飾語に気を付ける
- 回りくどい表現(冗長表現)を避ける
- 「こそあど」言葉を多用しない
- 程度を表す副詞は具体的な数字に置き換える
- 根拠を示して説得力を高める
- カタカナ語を乱用しない
- 主語と述語を対応させる(呼応表現)
このような記事を書いていて毎回思うのは、日本語というのは非常に奥が深く、だからこそ面白いということですね。米国の国務省が発表した『英語話者にとって習得するのが難しい外国語ランキング』というのがあり、日本語は最高ランク(最も難しい)に位置づけられているようです(参考)。日本で生まれ育った日本人でさえ、日本語は難しいと感じる場面が多々ありますから、外国人にとって世界最高難度なのも納得できますね。
日本語という、世界的に見ても非常に難しく複雑な言語を母国語に持ったことを光栄に思い、その文化や歴史を後世に伝えていきたいものです。

この記事を書いた人
田中泰章
Yasuaki Tanaka
プロフィール
自然の仕組みや環境問題、社会・教育制度などについて広い視点から考える自然科学者。2008年に東京大学大学院で博士号(環境学)を取得した後、東京大学、琉球大学、米国オハイオ州立大学、ブルネイ大学など、国内外の大学で研究と教育に約15年間携わってきました。これまでに30報以上の学術論文を筆頭著者として執筆し、国際的な科学雑誌の査読者として多数の論文審査も行っています。大学教員としては、これまでに40名以上の学生(学部・修士・博士を含む)を研究指導し、若手研究者を育成してきました。専門は「人間と自然とのかかわり」で、人間活動が自然界に与える影響を生物学・化学・社会学などの複合的な視点から研究しています。