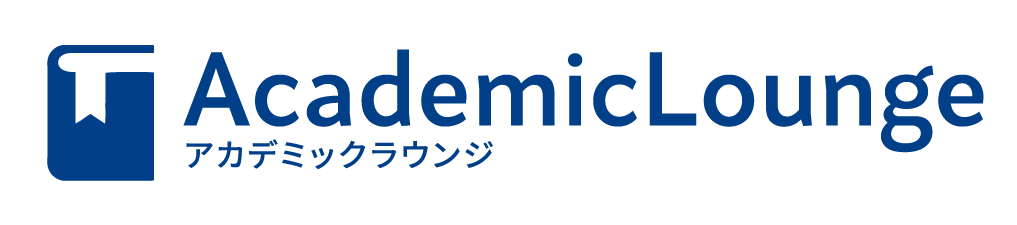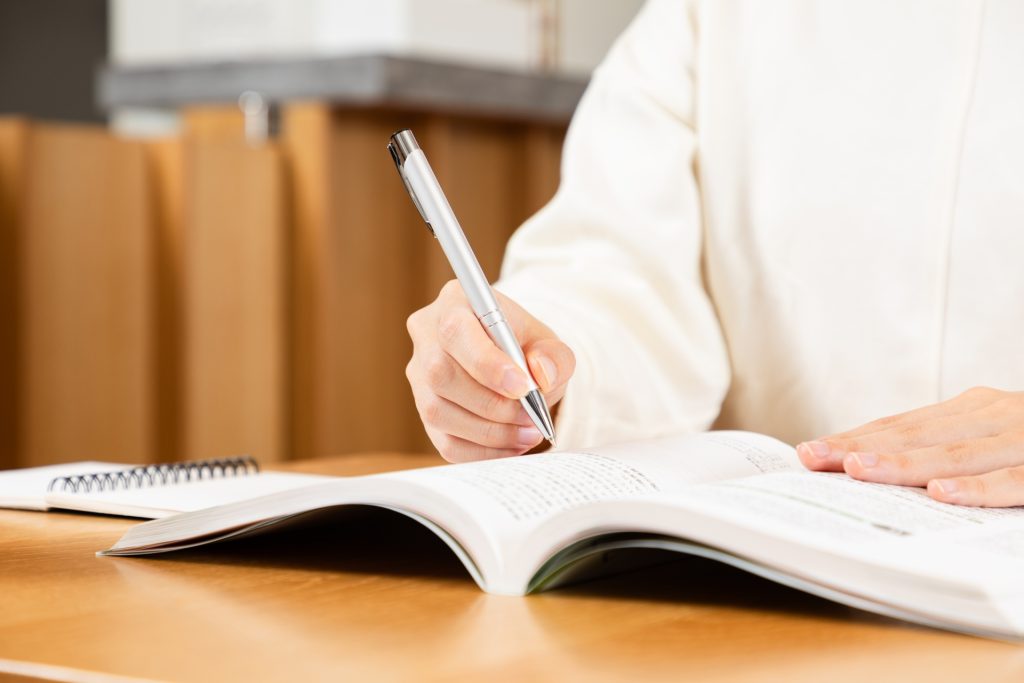大学院入試の研究計画書を自分で添削する方法:チェックポイント5選
大学院の入試では、研究計画書を提出するように求められることがよくあります。大学院は基本的に自分の興味があることを研究するために行くところなので、当然といえば当然ですが、受験生にとってはなかなか難しい課題です。
今回の記事では、研究計画書がうまく書けているかどうか、自分でチェックするときのポイントを5つお伝えしたいと思います。記事のタイトルには「大学院入試の〜」と書いていますが、受験生だけでなく、大学院生や研究者などが書く研究計画書にも当てはめられる内容です。自分が書いた計画書を読み返して推敲するときに、ぜひ参考にしてみてください。
魅力的な書き出しになっているか
研究計画書の書き出しは、多くの人が知っている、あるいはイメージできるような基本的なことから始めるのが良いでしょう。例えば、新聞、テレビ、ヤフーやグーグルなどの一般向けネットニュース、などで話題になるくらいのレベルです。
なぜこのような話題から書き始めるかというと、(1)読者対象を広げるため、そして(2)話題性が高いため、です。
(1)の「読者対象」というのは、文章を書くときは常に意識しないといけない視点です。一般大衆向けに文章を書くのであれば、一般の人たちが知っていることから書き始める必要がありますし、研究者向けに論文を書くのであれば、その分野の研究者が知っていることから書き始めます。書き出しを専門的な内容にすればするほど、読者対象を絞ることになります。
大学院受験で提出する研究計画書は、通常はその大学の教員が採点するので、読者としては大学教員を想定して書くことになります。しかし、ここで注意しないといけないのは、自分が取り組もうと思っている研究に非常に近い分野の教員が採点するとは限らないということです。一つの計画書を複数人の教員で採点することもありますし、基本的には「誰が採点するのか分からない」と思ったほうが良いです。そのため、自分が応募する大学の専攻やコースの教員を見て、その中の誰が読んでも理解できるくらい、一般的な話題から書き始めるようにしましょう。
(2)の「話題性」もある程度は意識します。本来、学術的な研究というのは話題性がある・なしに関わらず、純粋に自分の興味・関心にもとづいて行えば良いと私自身は思っています。しかしながら、大学院の入試には定員があるため、話題性のない研究テーマより、話題性のある研究テーマのほうがどうしても優先されることが多いです。この辺りは審査する教員の考え方にもよりますが、少しでも合格する可能性を上げるためには、話題性も意識しながら計画書の書き出しを考えるのが良いでしょう。
研究目的は具体的に書かれているか
「研究目的」は、なるべく具体的に書くようにしましょう。例えば、次の研究目的を読んでみて、具体性に欠けているのが分かりますでしょうか。どの辺りが具体性に欠けているか考えてみてください。
本研究は、環境変化が河川に生息する生物に与える影響を明らかにすることを目的とする。
「環境変化」だけではどんな環境の変化(水温や水質、改修工事など)に注目するのか分かりませんし、「河川に生息する生物」も微生物から大型動物まで、いろいろな種類が生息している可能性があります。「影響」についても、生態学的な影響もあれば、生物学的な影響、化学的な影響など、さまざまな視点が考えられますので、やはり具体性に欠けています。
このように対象や視点の解像度を上げていくと、例えば次のように具体的に記述することができます。
河川の護岸工事が、そこに生息する両生類の多様性および個体数に与える影響を明らかにする。
研究目的を具体的に書くのが難しいという方は、もっと先行研究を読み込む必要があります。その研究分野について詳しくなればなるほど、現在の課題が鮮明に見えてくるようになり、研究目的を具体的に書けるようになると思います。
研究の意義は書かれているか
「研究目的」を書いたら、「研究の意義」も書くようにします。順番としては、研究の意義を書いてから研究目的を書いても問題ありません。研究の意義、つまり何のためにその研究をするのか、その研究をしてどうなるのかを説明することによって、自分の研究の大切さを審査員にアピールします。
できれば複数の視点から研究の意義を書いてみることをおすすめします。学術的な意義、理論的な意義、技術的な意義、社会的な意義、教育的な意義、倫理的な意義、歴史的な意義、地域的な意義、国際的な意義など、同じ研究でもさまざまな視点から意義を考えてみます。複数の視点から意義を書くことで、その研究の大切さをさまざまな分野の人にアピールでき、どんな分野の審査員が見たとしても高評価が得られる可能性が高くなります。
研究方法は具体的に、順序立てて書かれているか
大学院入試の研究計画書を作成するうえで、一番難しいのが「研究方法」だと思います。受験生の間で一番差がつく項目といっても良いかもしれません。研究の背景や意義などは、先行研究を調べながら何となく書けてしまうかもしれませんが(「何となく」書いたもので十分、という意味ではありません)、研究方法というのは自分が実際に何をするのかを説明しないといけないので、しっかりとしたビジョンを持っていないとなかなか書けません。
一つの方法としておすすめしているのは、番号を付けながら計画をリスト化していくことです。「1. ・・・」「2. ・・・」「3. ・・・」というように、番号を付けて計画を書いていくことで、自分がどういう順番で何をしようとしているのか分かりやすく整理できるはずです。
研究目的と同じように、ここでもなるべく具体的に書くということを意識してください。例えば次のような内容を書くと、計画が具体化していきます。
- いつ行うのか(時期)
- どこで行うのか(場所)
- 何を使って(あるいは誰を対象にして)行うのか(研究対象)
- 何をするのか(作業工程)
- 得られた結果をどうやってまとめるのか(データの分析方法、統計解析の方法など)
「研究方法」のなかで、その研究を行う目的や意義を再度説明したり、「・・・とは」のように基礎知識を説明したりする方をたまに見受けますが、これは良い構成ではありません。「研究方法」では、上記のような実際の行動に関することだけを説明するようにしてください。
参考文献の書式は統一されているか
論文と違って、研究計画書は比較的短いので、それほど多くの参考文献を書くことはないと思いますが、それでも書式は統一するようにしましょう。文献リストの書式は、こちらの記事で書いたように色々あります。
出版年を括弧で囲うのか囲わないのか、ページ数にppを付けるのか付けないのか、雑誌名を斜字体にするかどうかなど、文献の書式には細かい違いがたくさんあります。研究計画書では、文献の書式までは指定されないことが多いので、もし指定されていなければ、どの書式でも自分が好きなものを選べば大丈夫です。
まとめ
以上が研究計画書を自分で添削するときの5つのポイントでした。
- 魅力的な書き出しになっているか
- 研究目的は具体的に書かれているか
- 研究の意義は書かれているか
- 研究方法は具体的に、順序立てて書かれているか
- 参考文献の書式は統一されているか
一番良いのは誰か他の人にチェックしてもらうことだと思いますが、そのような人が周りにいないときは、なるべく客観的な視点に立って、この5つのポイントをチェックしてみてください。

この記事を書いた人
田中泰章
Yasuaki Tanaka
プロフィール
自然の仕組みや環境問題、社会・教育制度などについて広い視点から考える自然科学者。2008年に東京大学大学院で博士号(環境学)を取得した後、東京大学、琉球大学、米国オハイオ州立大学、ブルネイ大学など、国内外の大学で研究と教育に約15年間携わってきました。これまでに30報以上の学術論文を筆頭著者として執筆し、国際的な科学雑誌の査読者として多数の論文審査も行っています。大学教員としては、これまでに40名以上の学生(学部・修士・博士を含む)を研究指導し、若手研究者を育成してきました。専門は「人間と自然とのかかわり」で、人間活動が自然界に与える影響を生物学・化学・社会学などの複合的な視点から研究しています。