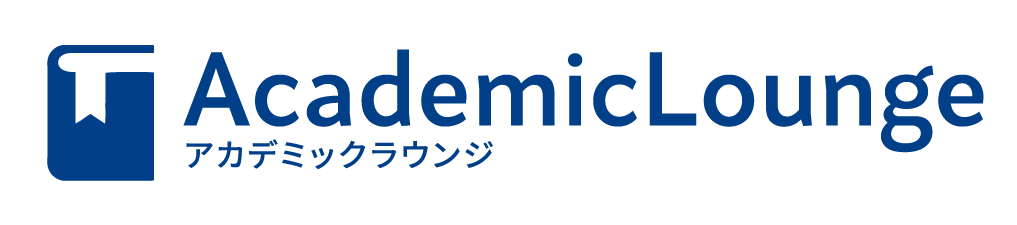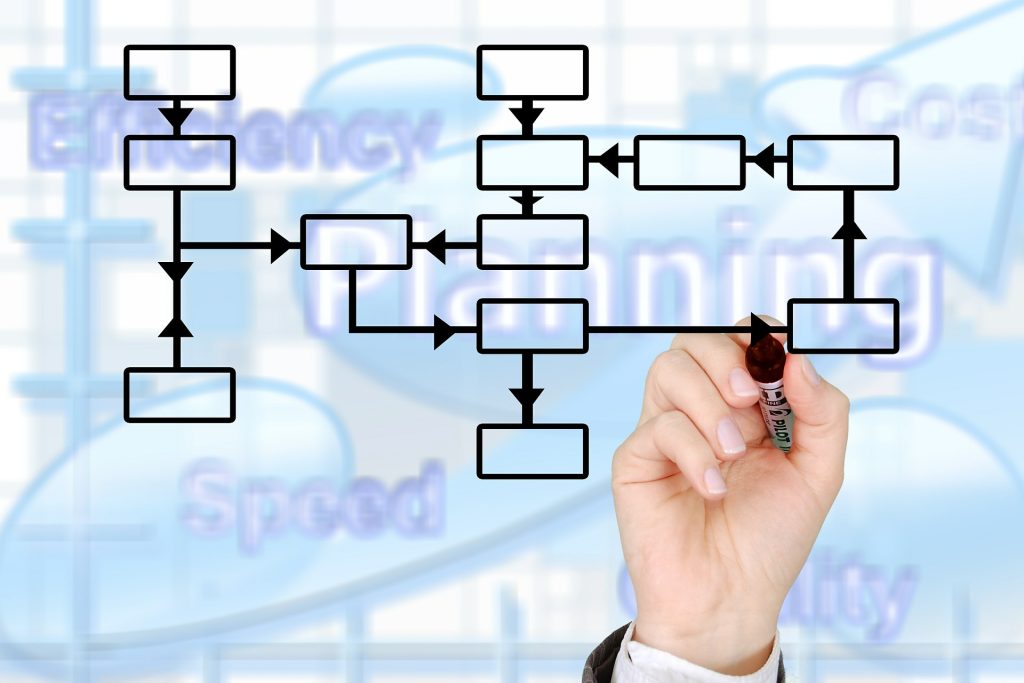学位授与機構・学修成果レポートの書き方
今回の記事では、大学改革支援・学位授与機構(以下、学位授与機構と略します)に提出する「学修成果」レポートの書き方を解説していきます。学位授与機構による学位の授与制度は、短大や専門学校などを修了した人たちが大学卒業資格(学士)を取得するための制度です。追加で授業科目を履修するとともに、必要な課題を提出したり面接を受けたりすることで、学士資格の審査を受けることができます。
その中で重要な評価材料となるのが、「学修成果」と呼ばれるレポートです。多くの大学では、4年生のときに卒業論文を作成して提出しなければなりませんが、それの代わりのようなイメージで「学修成果」が課されているわけです。「学修成果」は必ずしもレポートではなく、音楽や美術などの芸術分野では、演奏・創作・作品などでも良いようです。
学位授与機構による学位の授与制度についてもっと知りたい方は、こちらのWebサイトをご覧ください。
今回の記事では、「学修成果」レポートを提出する方々を対象にして、その基本的な書き方を解説していきます。
レポートのテーマ設定
まずレポートのテーマは、自分が申請しようとしている専門分野に関連するものでなければなりません。以下は、学位授与機構が公表している、レポートのテーマや内容に関する全般的な注意事項です。
レポートは、学位の取得を希望する者が、選択した専攻の区分において学士の水準の学力を有しているかどうかを審査する資料として提出を求めているものです。したがって、それぞれの専攻において学士の水準として十分な学力を身につけていること、また、相応の量の学修に基づいて作成されていることが判定できる内容でなければなりません。
レポートの内容は、各自が設定したテーマについて、根拠に基づいてあなた自身の考察・意見を論述したものであることが求められます。ただし、調査や実験を必須とするものではありません。また、指導教員の指導のもとに作成されたものである必要はありません。
「単に統計や調査の結果を述べただけのもの」、「事例研究等において事実の推移を単に記録しただけのもの」、「文献等を単に要約しただけのもの」、「外国語の論文等を単に翻訳しただけのもの」など、「あなた自身の考察や意見がないもの」や「主張や感想を根拠なく述べただけのもの」は、この制度におけるレポートの内容としては不適切です。
大学改革支援・学位授与機構、「新しい学士への途」令和7年度版
特に最後の段落が重要で、単に文献や資料を整理したり要約したりしただけのものや、筆者自身の考察や意見がないもの、主張や感想を根拠なく述べただけのものでは不十分ということです。どれも、学術的な論文やレポートとしては基本的なことですが、学術的な文章を書き慣れていない人にとっては、まずはこの辺りが一つ目の難しいポイントになりそうです。
ここからはレポートの内容に関する評価基準です。いずれも学位授与機構から公表されている項目(またはそれを要約したもの)で、大事なポイントを分かりやすく解説していきます。
評価基準①:レポートの目的や意義が明確に示されていること
「目的」とは、そのレポートの中で明らかにすることです。上述したように、単にこれまでの文献を整理するとか、自分の経験・主張をつづる、といった内容は「目的」として不十分です。文献を整理して何を明らかにしたいのか、自分の経験から何を論じたいのか、学術的な目標を持って「目的」を設定する必要があります。
「目的」を書いたら、「意義」も書くようにします。順番としては、「意義」を書いてから「目的」を書いても問題ありません。レポートの意義、つまり何のためにそのレポートを書くのか、そのレポートを書いてどうなるのかを説明することによって、自分のレポートの大切さを読者にアピールします。
できれば複数の視点からレポートの意義を書いてみることをおすすめします。学術的な意義、理論的な意義、技術的な意義、社会的な意義、教育的な意義、倫理的な意義、歴史的な意義、地域的な意義、国際的な意義など、さまざまな視点から自分のレポートの意義を考えてみます。
「目的」や「意義」の記述についてはこちらの記事もご覧ください。
評価基準②:文献や資料(先行研究)に基づいて書かれていること
学修成果レポートは、学術的な文献や資料に基づいて書く必要があります。例えばレポートの前半では、これまでにどのような研究が行われてきたのかを紹介し、自分が論じようとしているテーマの背景を概説します。レポートの後半では、自分の考察や解釈を裏付けるような文献に言及することで、自分の主張の妥当性を示します。
関連する文献や資料を随所で提示することによって、筆者の主張の説得力が増し、レポートの学術的な評価が高まります。
評価基準③:適切な方法を用いていること
文献研究にしても実証研究にしても、どのような方法でその成果を得たのか詳細に記述する必要があります。文献研究であれば文献の収集や整理の方法、実証研究であれば調査や実験の方法などです。例えばアンケート調査であれば、いつ・どこで・誰に・どんなアンケートを取ったのか、細かく記述します。
また、調査や実験を行うと、データ(量的データ・質的データ)が得られることも多くあります。データを適切な方法でまとめたり統計解析したりできているかどうかも評価の対象となります。
「研究方法」の記述についてはこちらの記事もご覧ください。
評価基準④:考察が明瞭かつ論理的に述べられていること
「考察」というのは、研究成果(調査や実験の結果)について、自分の解釈や推測、先行研究との比較などを通して、議論を展開することです。多くの学生にとっては、論文やレポートの中で最も難しく感じる項目だと思います。ありがちな「考察」として、結果を羅列しているだけだったり、議論が論理的に構成されていなかったりすることがありますが、これらはいずれも良い考察とは言えません。自分の解釈や推測、主張などがいかに妥当かということを、根拠を示しながら展開していくことが大切です。
「考察」の書き方についてはこちらの記事もご覧ください。
評価基準⑤:文献・資料等の引用が適切になされていること
レポートを書くうえで参考にしたり引用したりした文献や資料は、本文中に記載するとともに、レポート末尾にはそのリストをまとめる必要があります。これらが記載されていなかったり、記載方法が文献によってバラバラだったりすると、良いレポートとして評価されませんので注意しましょう。
大学改革支援・学位授与機構、「新しい学士への途」令和7年度版
- 文章・図表等を引用する場合は、引用部分を「 」等で明示するとともに、出典としてその著者名、文献名、発行年やページを明らかにすること。なお、引用部分を明示していても、文献の文章を複数ページにわたってそのまま引用することは適切ではありません。
- あなた自身の意見や考察と参考文献からの引用等の内容とが判別できるように書かれていること。
- レポートを作成する上で参考にした文献、資料等については、レポートの最後に適切な形式にしたがって参考文献としてまとめて提示すること。
文献の記載方法は主にハーバード方式(著者名方式)とバンクーバー方式(引用順方式)に分けられます。どちらの方式で書くかの指定はないようですので、多くの人にとって書いたり読んだりしやすい、ハーバード方式(著者名方式)で記載すれば良いと思います。
参考文献の記載方法についてはこちらの記事もご覧ください。
まとめ
以上、「学修成果」レポートの基本的な書き方と評価基準をまとめてみました。「レポート」とはいえ、書き方や評価基準は一般的な卒業論文と共通している部分がとても多いということが分かります。
また、レポートの形式に関する細かい指定も多くあります。例えば、ページ数は10〜17ページ、1ページの行数は30行、1行あたりの文字数は40文字、表紙・目次・要旨を作成する、ページ番号を付ける、などです。詳しくは、学位授与機構がホームページに公開している「新しい学士への途」をダウンロードしてご覧ください。
アカデミックラウンジでは、学修成果レポートの作成に関するご相談も承っております。作成の初期段階から原稿の推敲段階まで、さまざまなご相談に対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

この記事を書いた人
田中泰章
Yasuaki Tanaka
プロフィール
自然の仕組みや環境問題、社会・教育制度などについて広い視点から考える自然科学者。2008年に東京大学大学院で博士号(環境学)を取得した後、東京大学、琉球大学、米国オハイオ州立大学、ブルネイ大学など、国内外の大学で研究と教育に約15年間携わってきました。これまでに30報以上の学術論文を筆頭著者として執筆し、国際的な科学雑誌の査読者として多数の論文審査も行っています。大学教員としては、これまでに40名以上の学生(学部・修士・博士を含む)を研究指導し、若手研究者を育成してきました。専門は「人間と自然とのかかわり」で、人間活動が自然界に与える影響を生物学・化学・社会学などの複合的な視点から研究しています。