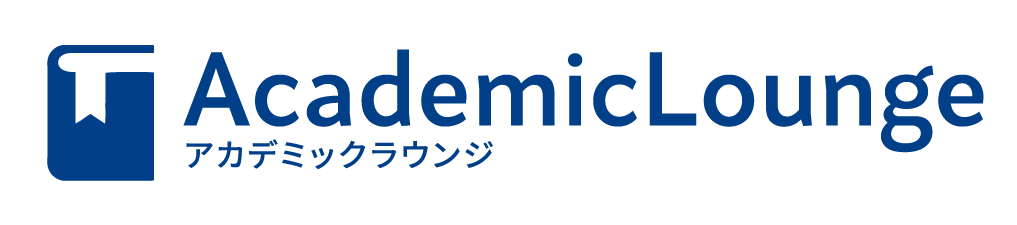文献研究と実証研究の違い、論文と感想文の違い
今回の記事では、(1)文献研究や実証研究など、主な学術論文の種類と、(2)これらの学術的な文章と文学的な文章との違いをまとめておきます。これから研究計画を立てるという方や、大学の卒業論文やレポートがどういうものなのか分からないという方、論文と感想文との違いが分からない方などは、ぜひ参考にしてみてください。
ちなみに「レポート」にはさまざまな種類があり、学術論文のように目的や仮説を設定し、結論に向けて論理的に説明していくタイプのレポートもあれば、本を読んだ後に書く読書レポート、授業で学んだことをまとめるような学習レポートなどもあります。紛らわしいので今回の記事では「レポート」という言葉は使いませんが、学術論文と同じように構成していくタイプのレポートの場合は、今回の記事の内容をそのまま当てはめることができます。
文献研究と実証研究
まず、学術論文の種類は文献研究型と実証研究型に大別することができます。
文献研究とは、すでに公表されている論文や資料などを使って行う研究です。過去の文献を集めて整理したり分析したりすることによって、これまでに知られていなかったことや新しい見方・解釈などを提示することを目指します。
それに対して実証研究では、フィールドワークや実験、アンケート調査、インタビュー調査などから自分だけのデータを取得して、そのデータを使って研究を行います。事前に仮説や課題(リサーチクエスチョン)を設定し、それを検証しようとする研究です。
文献研究と実証研究のどちらを行うかは、研究目的によって変わってきます。一般に文献研究は、歴史や文学などの文系の分野で多く見られますが、文系でもフィールドワークやインタビューなどを行えば実証研究といえます。
一方、実証研究は理系の分野で多く見られますが、理系でも総説(レビュー)は文献研究といえるでしょう。また、実証研究を行うにしても、事前に先行研究をよく調べる必要がありますので、そういう意味では実証研究の中には文献研究も含まれるといってもいいかもしれません。
文献研究の種類
文献研究にもいくつかの種類がありますが、ここでは文系の代表的な二つを紹介します。一つは論争型、もう一つは伝記型です(尾崎 2025)。
論争型の論文というのは、賛否両論ある問題を研究テーマに据えて、賛成と反対の両方の立場からその理由や背景を論じていき、最終的には著者の見解を述べます。政治、文化、教育など、賛否両論あるテーマは無数にありますので、どんな分野でもテーマを設定しやすいといえます。
伝記型の論文というのは、特定の人物や出来事、文化、概念などについて歴史的な事実を掘り起こしながら、新たな発見を提示します。単に過去の文献や先行研究についてまとめるのではなく、まとめた結果明らかになったことや、著者独自の見方・解釈を示すことが重要です。
実証研究の種類
実証研究にもいくつかの種類がありますが、大きく分けると観察(観測)型と実験型に分けられます。
観察(観測)型では、人間社会や自然環境のなかで実際に起きていることをそのまま観察(観測)します。例えば、人間がどのように行動しているかを観察したり、毎日の気温がどのように変化しているかを観測したりするような研究です。
実験型というのは、文字通り実験室のなかで行う化学や物理などの実験をイメージすれば良いですが、必ずしも実験室の中だけではなく、屋外で実験を行うこともできます。観察(観測)型と異なるのは、人間が何らかの操作や介入を行い、意図した状況を人工的に作り出すということです。
論文と感想文の違い
ここまで論文の種類について見てきましたが、いずれも学術的な文章であることに変わりはありません。文系であれ理系であれ、文献研究であれ実証研究であれ、学術的な文章(論文)には共通したルールのようなものがあります。
ここでは、論文に代表される学術的な文章と、感想文や小説に代表される文学的な文章との違いを整理しておきます。
学術的な文章
論文、レポート、研究計画書、調査報告書、専門書など
文学的な文章
感想文、小説、詩、日記など
一つ目の違いは、文章の展開方法です。文学的な文章では、自分の主張を主観的に展開できるのに対し、学術的な文章では自分の主張を客観的に展開する必要があります。
「自分の主張を客観的に展開する」とは、自分の主張を述べるだけでなく、なぜそのように考えるのかという理由や根拠を論理的に説明するということです。具体的には、自分の研究結果や過去の研究論文、公表されている資料やデータなどに言及しながら、自分の主張の妥当性を説明します。さまざまな視点から自分の主張の妥当性を説明し、少しでも多くの読者に納得してもらうことを目指します。
二つ目の違いは、表現の多義性です。文学的な文章では、あいまいな表現や読者によって解釈が分かれるような表現も使われ、意味が複数に取れる(多義的な)表現・文章でも問題ありません。一方で学術的な文章では、そのような表現は使わず、誰が読んでも同じように解釈でき、同じものや状況をイメージできるように文章を作成します。
例えば、「すごく」「極端に」「少し」はいずれも「程度」を表す副詞ですが、このような抽象的な表現を学術的な文章で使うときは注意を払います。これらの表現からイメージする「程度」は、読者によって違うかもしれないからです。代わりに具体的な数値で「程度」を示せば(例えば「20%増加した」のように)、すべての読者が同じ「程度」をイメージできるようになり、学術的な文章としてふさわしい表現になります。
まとめ
今回の記事では、学術論文には文献研究型(論争型・伝記型)と実証研究型(観察型・実験型)があること、そしてそれらの学術論文と文学的な文章との違いについてまとめました。研究計画を立てるときは、まずは自分がどのようなタイプの研究を行おうとしているのか明確にしましょう。自分の興味・関心があるテーマを選ぶことはもちろんですが、取り組みやすい方法で研究を進めることも大切です。興味・関心と実現可能性の両面から、どのような研究を行うのか考えてみるのが良いと思います。
<参考文献>
課題に応える 卒論に活かせる 大学生のためのレポートの書き方
〈改訂版〉大学生のための 論文・レポートの論理的な書き方
ゼロから始める 無敵のレポート・論文術 (講談社現代新書)

この記事を書いた人
田中泰章
Yasuaki Tanaka
プロフィール
自然の仕組みや環境問題、社会・教育制度などについて広い視点から考える自然科学者。2008年に東京大学大学院で博士号(環境学)を取得した後、東京大学、琉球大学、米国オハイオ州立大学、ブルネイ大学など、国内外の大学で研究と教育に約15年間携わってきました。これまでに30報以上の学術論文を筆頭著者として執筆し、国際的な科学雑誌の査読者として多数の論文審査も行っています。大学教員としては、これまでに40名以上の学生(学部・修士・博士を含む)を研究指導し、若手研究者を育成してきました。専門は「人間と自然とのかかわり」で、人間活動が自然界に与える影響を生物学・化学・社会学などの複合的な視点から研究しています。