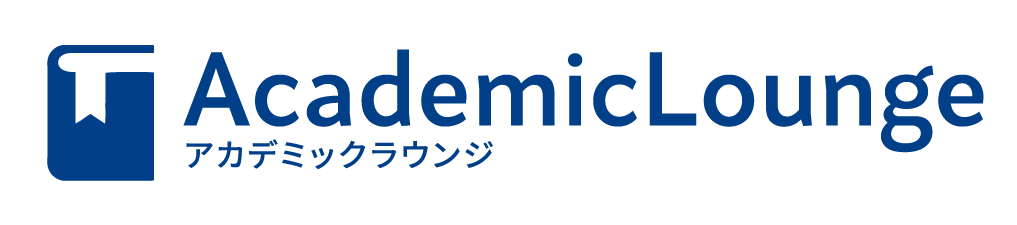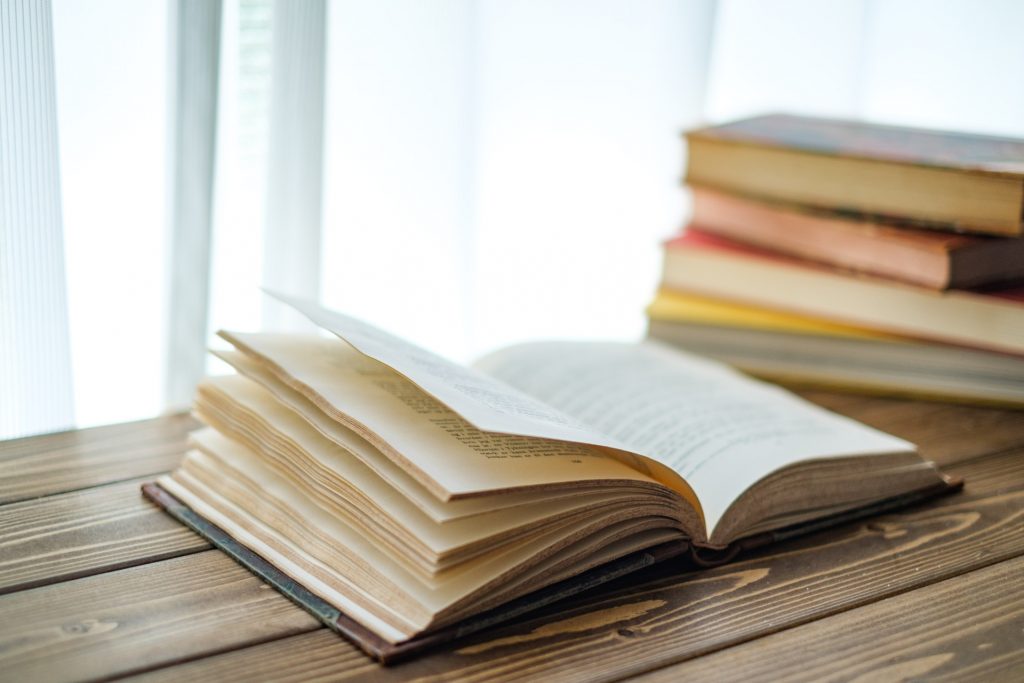日本語論文の校正・添削:「の」を連続させない
今回の記事では、分かりやすい文章を書くコツの一つとして、「の」を連続させないということを取り上げたいと思います。
日本語の「の」は便利な助詞で、いろいろな場面で使うことができますが、その反面、多用すると文意が正確に伝わりにくくなってしまいます。多くの参考書では、「の」が連続して3つ以上入るのはNGとされています。
そこで今回は「の」が3つ入った例文を示しながら、それをどのように修正(校正)できるのかご紹介したいと思います。なお、すべての例文はChatGPTで作成したもの(もしくはそれを一部改変したもの)です。
なぜ「の」を連続させないほうが良いのか?
まず、なぜ「の」を連続させないほうが良いのか考えてみましょう。次の例文を読んでみてください。
同僚の友達の話の内容が気になった。
「同僚が話している」内容なのか、「同僚の友達が話している」内容なのか、意味が二通りに解釈できます。もう一例挙げてみます。
実験の条件の設定の違いが結果に影響した。
意味は伝わりますが、表現が冗長的で、なんとなく分かりにくい印象を受けるのではないでしょうか。
このように、「の」が連続すると文意が読者に正確に伝わらなかったり、読者が文意を理解するのに時間がかかったりします。読者にとって分かりやすい文章にするためには、「の」をあまり連続させないほうが良いということです。
それでは「の」が3つ以上連続する例文を挙げながら、その修正方法を解説していきます。
1つの名詞にまとめる
まずは「の」を削除して、2つの名詞を1つにまとめるパターンです。(場合によっては3つ以上の名詞をまとめられることもあります)
例文1
都市の再開発の計画の内容は、住民にまだ知らされていない。
「再開発の計画」は、「再開発計画」という1つの名詞にできますので、次のように修正できます。
都市の再開発計画の内容は、住民にまだ知らされていない。
例文2
作家の作品のテーマの多様性が、読者の関心を引きつけている。
「作品のテーマ」は、「作品テーマ」という1つの名詞にできますので、次のように修正できます。
作家の作品テーマの多様性が、読者の関心を引きつけている。
例文3
子どもの言語の発達の過程は、家庭環境に大きく影響される。
「言語の発達」は、「言語発達」という1つの名詞にできますので、次のように修正できます。
子どもの言語発達の過程は、家庭環境に大きく影響される。
「の」を言い換える
次は、「の」が他の助詞に言い換えられるパターンです。
例文4
芸術の分野の表現の多様性が、国際的に再評価されている。
「芸術の分野」は、「芸術分野」という1つの名詞にできますので、まずは次のように修正できます。
芸術分野の表現の多様性が、国際的に再評価されている。
さらに、「芸術分野の表現」というのは、「芸術分野における表現」と言えますので、次のように修正すると「の」を1つに減らすことができます。
芸術分野における表現の多様性が、国際的に再評価されている。
例文5
動物の行動の研究の積み重ねによって、種の適応戦略が明らかになってきた。
「動物の行動」は「動物行動」という1つの名詞にできますので、まずは次のように修正できます。
動物行動の研究の積み重ねによって、種の適応戦略が明らかになってきた。
さらに、「動物行動の研究」というのは、「動物行動に関する研究」と言えますので、次のように修正すると「の」を1つにできます。
動物行動に関する研究の積み重ねによって、種の適応戦略が明らかになってきた。
不要な語を削除する
「の」が連続している場合、不要な語や冗長な語が入っていることもよくあります。
例文6
親の期待の重さの影響が、子どもの進路選択に表れている。
「期待の重さの影響」という表現が冗長で、「期待」だけで十分に意味が伝わりますので、次のように修正できます。
親の期待が、子どもの進路選択に表れている。
例文7
教員の授業の進め方の違いが、学習成果に差を生んでいる。
「進め方の違い」という表現が冗長的で、「進め方」だけで十分に意味が伝わりますので、次のように修正できます。
教員の授業の進め方が、学習成果に差を生んでいる。
例文8
歴史の教育の内容の見直しが、現在検討されている。
「歴史教育」とまとめるか、「教育内容」とまとめるか、迷うところですが、とりあえず「教育内容」としてみます。
歴史の教育内容の見直しが、現在検討されている。
これでも問題はありませんが、「教育内容の見直し」は少し冗長な印象で、「教育」だけでも意味が伝わりそうです。そこで、「内容」を削除し、「歴史教育」とまとめてみました。
歴史教育の見直しが、現在検討されている。
例文9
音楽のリズムの変化の特徴は、感情の変動に関係している。
「リズムの変化」は「リズム変化」と、1つの名詞にできますので、まずは次のように修正できます。
音楽のリズム変化の特徴は、感情の変動に関係している。
ただ、「特徴」はあってもなくても文意はほぼ変わらないので、削除できそうです。
音楽のリズム変化は、感情の変動に関係している。
さらに、「変化」と「変動」は似たような意味なので、片方を削除しても良いでしょう。
音楽のリズムは、感情の変動に関係している。
音楽のリズム変化は、感情に関係している。
例文10
農業の技術の進歩の速度が、食料自給率の向上に貢献している。
「農業の技術」は「農業技術」と、1つの名詞にできますので、まずは次のように修正できます。
農業技術の進歩の速度が、食料自給率の向上に貢献している。
また、「速度」が「向上に貢献している」わけではなく、「進歩」そのものが「向上に貢献している」ので、「速度」は削除したほうが良さそうです。
農業技術の進歩が、食料自給率の向上に貢献している。
例文11
日本の高齢化の進行の速度は、他国と比べて顕著である。
「進行の速度」は「進行速度」と、1つの名詞にできますので、まずは次のように修正できます。
日本の高齢化の進行速度は、他国と比べて顕著である。
ただ、「速度が他国と比べて顕著」では、速度が早いのか遅いのか分かりませんので、「速度」は削除し、「進行が他国と比べて顕著」にします。こうすると、「他国に比べて進むのが早い」という意味になります。また、「日本の高齢化」は「日本における高齢化」にできそうです。
日本における高齢化の進行は、他国と比べて顕著である。
例文12
若者の価値観の形成の背景は、メディアの影響と深く関係している。
「価値観の形成」は「価値観形成」と、1つの名詞にできますので、まずは次のように修正できます。
若者の価値観形成の背景は、メディアの影響と深く関係している。
また、「背景」が「メディアの影響と関係している」というより、「背景」を含めた形成プロセスに「メディアが関係している」ということだと思いますので、「背景」と「影響」はともに削除できそうです。
若者の価値観形成は、メディアと深く関係している。
ただ、これでも少しぎこちないので、私なら次のように書くと思います。
若者が形成する価値観は、メディアの影響を強く受けている。
「名詞+動詞」に言い換える
ここからは、「名詞+名詞」を「名詞+動詞」に言い換えられるパターンです。これは「の」に限らず、名詞が連続していて読みにくいときに使える方法です。
例文13
社会の構造の変化の兆しは、各分野に見られる。
まずは「社会の構造」を「社会構造」にして、「の」の数を1つ減らします。
社会構造の変化の兆しは、各分野に見られる。
「社会構造の変化」は2つの名詞を「の」で連結している構造ですが、これを「社会構造が変化する」という「名詞+動詞」の構造にすると、「の」を使わない文にできます。
社会構造が変化している兆しは、各分野に見られる。
例文14
科学者の研究の動機の変化が、学問の方向性に影響を及ぼしている。
まずは「研究の動機」を「研究動機」にして、「の」の数を1つ減らします。
科学者の研究動機の変化が、学問の方向性に影響を及ぼしている。
「研究動機の変化」は、「研究動機が変化する」という「名詞+動詞」の構造に言い換えられますので、次のように「の」が1つだけの文に修正できます。
科学者の研究動機が変化し、学問の方向性に影響を及ぼしている。
例文15
企業の経営の方針の変更は、従業員のモチベーションに影響を与える。
「経営の方針」は「経営方針」という1つの名詞にできますので、まずは次のように修正します。
企業の経営方針の変更は、従業員のモチベーションに影響を与える。
さらに、「経営方針の変更」を「経営方針を変更する」という「名詞+動詞」の構造にすると、「の」が1つだけの文に修正できます。
企業の経営方針を変更すると、従業員のモチベーションに影響を与える。
例文16
国民の生活の質の向上が、政策の目的として重視されている。
まずは「国民の生活」を「国民生活」にして、「の」の数を1つ減らします。
国民生活の質の向上が、政策の目的として重視されている。
さらに、「質の向上」を「質を向上させる」という「名詞+動詞」の構造にすると、次のようになります。
国民生活の質を向上させることが、政策の目的として重視されている。
例文17
学生の研究の成果の発表が、学会で高く評価された。
「研究の成果」は「研究成果」と、1つの名詞にできますので、まずは次のように修正します。
学生の研究成果の発表が、学会で高く評価された。
「研究成果の発表」は、「研究成果を発表する」という「名詞+動詞」の構造に変えられ、あとは文の前半と後半をうまくつなげます。
学生が研究成果を発表したところ、学会で高く評価された。
まとめ
今回の記事では、「の」が連続する場合の校正方法をご紹介しました。
- 1つの名詞にまとめる
- 別の助詞に言い換える
- 不要な語・冗長な語を削除する
- 「名詞+名詞」を「名詞+動詞」に言い換える
文章を執筆・推敲・校正するときは、「の」が3つ以上続いたら(あるいは2つでも続いたら)、表現を修正できないか検討してみてください。
余談ですが、今回の例文をChatGPTで作ったときに、私は「『の』が3つ以上入った文を作って」と指示を出しました。色々な分野の例文をすぐに作ってくれるので、こういうときにChatGPTは非常に便利です。ただ、「不要な語・冗長な語が入った文を作って」とは指示していません。指示していないのにそういう語が入っている文が多々あり、おそらくChatGPTとしてはそういう語を必要だと判断しているのでしょう。それがChatGPTの現状ですが、ChatGPTや他のAIツールの問題についてはまた別の記事でまとめてみたいと思います。

この記事を書いた人
田中泰章
Yasuaki Tanaka
プロフィール
自然の仕組みや環境問題、社会・教育制度などについて広い視点から考える自然科学者。2008年に東京大学大学院で博士号(環境学)を取得した後、東京大学、琉球大学、米国オハイオ州立大学、ブルネイ大学など、国内外の大学で研究と教育に約15年間携わってきました。これまでに30報以上の学術論文を筆頭著者として執筆し、国際的な科学雑誌の査読者として多数の論文審査も行っています。大学教員としては、これまでに40名以上の学生(学部・修士・博士を含む)を研究指導し、若手研究者を育成してきました。専門は「人間と自然とのかかわり」で、人間活動が自然界に与える影響を生物学・化学・社会学などの複合的な視点から研究しています。