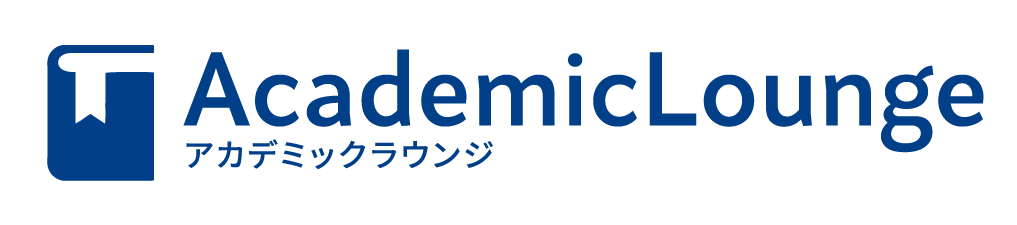質的研究の基本:採択される論文を書くために知っておきたいこと(前編)
近年、質的研究の論文を見かけることが多くなりました。数値では表現できない、豊かな現実を映し出す手法として発展してきた質的研究ですが、その歴史の短さに比して、すそ野の広がりは目を見張るものがあります。
質的研究はとても創発的で、やりがいのあるものです。一方で、統計学が苦手な学生さんが、「質的研究なら親しみやすいかも」といった安易な動機でスタートする姿が散見されるのも、実情としてあります…。しかしながら、(質的研究を行ったことのある人なら分かっていただけると思いますが、)安易に手出しすると、後で大変な苦労をします。
そんな質的研究について、検討段階からいかに向き合い、質の高い論文に仕上げていくのかという観点から、前編と後編に分けてお伝えします。
質的研究とは
質的研究がどのようなものであるかを一言で表現すると、「探索的な問いに答える研究手法」と言えます。Green&Thorogood(2018)によると、質的研究は以下の六点によって特徴づけられます。
- 自然主義
- 文脈の重視(その人や集団の置かれた状況への深い理解)
- 意味への着目(現象の奥にある意味を重視する)
- 省察(自分自身を絶えず振り返り続ける)
- 批判的視座(常識を疑う)
- 論理的推論
すなわち、実験などの特殊な状況ではない、対象者が生きている自然な状況・文脈における意味を大切にするものであり、省察や批判的視点、推論力が求められると言えそうです。
量的研究との違い
質的研究との対比として、量的研究が挙げられます。両者を比較しながらのほうが理解しやすいので、両者の異同を挙げながら、質的研究について探ってみましょう。
研究の領域では、長らく量的研究が一般に行われてきました。量的研究とは、実証主義に基づき、仮説検証によって普遍的な真理を追究しようとするものです。質問紙データや生体指標データを中心とした、数値データを統計的に分析し、結果はグラフや数値表、数式などで表現します。
対して質的研究は、認識論に基づいて、研究対象の文脈における、研究対象にとっての現実を描写しようとするものです。インタビューや観察、資料などから集めた文字(テキスト)や文章などのデータを主な分析対象とし、分析結果は、元となるデータのニュアンスを生かしながら、日常的な言葉に近い形で表現します(佐藤,2002)。
以下は、クレスウェル&クレスウェル(廣瀬訳,2022)による、質的研究と量的研究の比較表です。
| 質的研究 | 量的研究 | |
| デザインを生成する | ←ーーー→ | 規定されたデザイン |
| 参加者の視点 | ←ーーー→ | 研究者の視点 |
| 複雑な絵 | ←ーーー→ | 狭い絵 |
| 研究者のバイアスの存在 | ←ーーー→ | 研究者のバイアスは存在しない |
| 文脈/状況の重視 | ←ーーー→ | 人為的な状況設定 |
| オープンエンドなデータを収集 | ←ーーー→ | クローズドエンドなデータを収集 |
| 帰納的データ分析 | ←ーーー→ | 演繹的データ分析 |
| 柔軟な文章構成 | ←ーーー→ | 高度に構成された文章 |
これらから、質的研究とは量的研究の限界を乗り越えようとし、結果的には相補的な形で発展してきていることが理解できます。なお近年では、量的研究と質的研究を組み合わせた「ミックスメソッド」という手法も活用されており、より効果的な研究法を構築する試みがなされています。
質的研究の多様な分析方法
質的研究には、代表的なものとしてグラウンデッド・セオリー・アプローチ(Grounded Theory Approach:GTA)や、それを応用した修正版グラウンデッド・セオリー・アプローチ(Modified Grounded Theory Approach:M-GTA)、KJ法などがありますが、それ以外にも多様な分析方法があります。
ここでは一例として、サトウら(2019)による「質的研究法マッピング」の目次から、どのような研究法があるのかを見てみましょう。それぞれの章のタイトルは、この本で提案されている、実存性・理念性×構造・過程という四象限における質的研究法のマッピングを示しています。なお、目次はamazonの商品ページにも記載されています。
質的研究法マッピング(2019) サトウタツヤ (編集), 春日秀朗 (編集), 神崎真実 (編集)
目次(一部)
1章 「過程×実存性」――モデル構成
1-1 日誌法
1-2 TEA(複線径路等至性アプローチ)
1-3 ライフストーリー
1-4 ライフラインメソッド
1-5 iQOL(Individual Quality of Life)
1-6 回想法/ライフレビュー
2章 「構造×実存性」――記述のコード化
2-1 KJ法
2-2 テキストマイニング
2-3 SCAT(Steps for Coding and Theorization)
2-4 オープンコーディング
2-5 会話分析
2-6 PAC(個人別態度構造)分析
2-7 解釈記述アプローチ
3章 「構造×理念性」――理論構築
3-1 グラウンデッド・セオリー・アプローチ(GTA)
3-2 修正版グラウンデッド・セオリー・アプローチ(M-GTA)
3-3 生態学的アプローチ
3-4 エソロジー
3-5 マイクロエスノグラフィー
3-6 ビジュアル・ナラティブ
3-7 TAE(Thinking At the Edge)
3-8 自己エスノグラフィー
4章 「過程×理念性」――記述の意味づけ
4-1 ナラティブ分析
4-2 ディスコース分析
4-3 エスノメソドロジー
4-4 ライフヒストリー
4-5 解釈的現象学
ご覧いただくと分かるように、分析法の紹介だけでも大幅なスペースを要するほど、多様な分析法があります。そのため、自分が研究に取り組むに当たっては、明らかにしたいテーマや現象に対して、どういった分析が妥当かを丁寧に検討することが求められます。加えて、質的研究法では、分析する目的に沿って研究法そのものを創出していくという側面もあり、今後の研究の中で、あなた自身が創り出すものでもあるかもしれません。
質的研究の全体的な流れ
さて、質的研究の全体的な流れは、どのようなものでしょうか。分析方法によって多少の違いはありますが、共通するポイントを含めて解説したいと思います。
(1)構想・先行研究レビュー
研究を始めるときには、漠然とした問いが存在しています。現場での実践や、生活の実体験などで、「これってどうなっているのかな」などモヤモヤと考えることを、研究の問いとして明確化するために、関心のある領域にまつわる先行研究を読み込んでいきます。
以前は「質的研究は帰納的プロセスであり、質的研究者は協力者(対象者)から学ぶのだから、必ずしも文献レビューは必要ない」という考え方がありましたが、現在では文献レビューについての考え方も変わりました(クレスウェル&クレスウェル, 廣瀬訳,2022)。量的研究と同様に先行研究の丁寧なレビューを行い、そこから課題を抽出し、自分が取り組む研究を導かなくてはなりません。
なお、質的研究の計画書で「先行研究では明らかになっていないから本研究で取り組みます」といった論旨が散見されますが、これでは稚拙な印象になってしまいます。明らかになっていないことなど世の中には無数にありますし、そもそも研究する意義が低いから明らかにされていない可能性だってあるためです。先行研究の積み上げを基にして、「明らかになっていないから」以上の、本研究を行う意義を表明する必要があります。
(2)倫理的配慮
近年、倫理的配慮の重要性が高まっており、量的研究でも配慮が求められています。まして、インタビューや観察などで、協力者との接触時間が長く、かつ深層に迫る関わりをすることもある質的研究においては、細心の配慮が求められます。個人情報の保護や、自由意志に基づいて研究参加を決められること(中断も可能であること)、協力者の負担への配慮などを文書に明記し、それらについて理解して同意した方にのみ、協力いただく手続きとなります(インフォームドコンセント)。
所属する機関に倫理審査委員会がある場合は、必ず審査を受けましょう。事前に審査・指摘を受けることで、必要な配慮に気付くことができますし、論文投稿にあたっては、倫理的配慮は厳しく問われるからです。審査を受けているかどうかを投稿時に確認されることがあり、論文への記述も求められます。
また、研究の対象となる方々を論文の中でどのように表現するかにも、研究者の態度が現れます。質的研究の論文では、「協力者」「参加者」「インフォーマント」などの表現がなされ、「被験者」「被調査者」といった言い回しはあまりしません。あくまで、研究者は、対象となる方の世界に身を置かせていただき、教えていただく立場なのです。
なお、最近では、オンラインでインタビューを行うことも増えました。録画の場合には特にデータの情報量が多く、データが漏洩した際のリスクも高くなることから、研究の目的にもよりますが、音声のみの取得とすることも検討しましょう。また、録画データを取得する場合には、データ保管の方法など、更なる配慮が必要でしょう。
(3)フィールドエントリー
フィールドエントリーとは、研究の対象となる現場(フィールド)に入っていくことを指します。例えば、子どもたちの行動を観察するために教育現場に行く場合や、特定の疾患を持つ人たちの自助グループに参加させてもらう場合などがあります。研究形態によっては、フィールドエントリーを要しない場合もありますが、特に観察研究では必ず行うことであり、質的研究に取り組もうとする方にとって、最初の関門とも言えるようです。できるだけ自然な形で入っていくことを目指すと同時に、自分自身がフィールドに与える影響を自覚する必要があります。
なお、何らかの組織に入っていく場合には、事前にその責任者に対して研究の目的や倫理的配慮について説明をしつつ、逆にそのフィールドの中で研究者が気を付けるべきことなどを教えてもらいます。
(4)データ収集
さて、いよいよデータを収集します。収集方法は、インタビューや観察、アンケートの自由記述など、様々な形態がありますが、共通して重要なことは、「研究協力者への敬意を持ち、謙虚な気持ちで取り組む」ことです。研究協力者にとって、普段あまり話さないようなことを、よく知らない研究者に対して話すことは、心理的ハードルが高いものです。「どのように見られているのだろうか」「どのように公表されるのだろうか」と不安に思うことも想像に難くありません。(2)で述べた倫理的配慮を踏まえて、丁寧な対応が求められます。
(5)分析
データを収集したら、分析に進みます(GTAのように、データの収集と分析を並行して行う研究法もあります)。ここでは、質的研究に特有の課題である「研究者の主観/バイアス」をどう扱うのかが重要となります。主観を排する方向で努力するというよりも、「主観はある」と理解・内省しながら、自分自身の主観が分析にどのような影響を与えているかに自覚的であろうと努力します。一方で、「主観/バイアスが存在すること」と、「独りよがりであること」は異なります。そのため、可能であれば、協力者(対象者)にチェックしてもらったり、指導者や同僚とディスカッションしたりすることで、独りよがりな分析にならないように留意しながら進めていきます。
また、質的研究の質を高めるためには、信頼性(再現性)と妥当性(調べたいものを適切に調べられているのか)の問題についても意識する必要があります。これらについては、量的研究の概念をそのまま当てはめることはできません。サトウ(2007)はこの点に関して、「手続き的再現性(同様の研究を行うことが出来るように手続きを詳述すること)は重要である。すなわち、研究方法が再現可能でなければならない」としています。すなわち、論文において、分析の手順をできる限り明確に、分かりやすく記述することで、再現性の問題を乗り越えようとしています。また、妥当性に関しても、研究計画の段階から、どのような対象に、どのような方法でアプローチしたら、自身のリサーチクエスチョンに迫ることができるのかを、同僚や指導者と相談しながら明確化していきます。
(6)論文執筆
最後に、論文の執筆についてです。本記事では便宜上、研究のステップを項目ごとに分けていますが、太田(2009)は、「質的研究」と「書く」ことはお互いに切り離すことができないと言っています。つまり、分析がまとまってから論文として仕上げるといった性質のものではないのです。分析しながら書き、そこで得た発想を反映してまた分析し、さらには追加で調査したり先行研究まで当たったり…という営為が繰り返し行われることが、質的研究の大きな特徴です。また、データ収集、分析、理論化、既述のプロセス全体を通して、自己を振り返り(省察)、研究を深めていく必要性があります(太田,2009)。
個人的には、研究背景のレビューについては、研究協力者を募集するより前にほぼ書きあげてしまうことをお勧めします。なぜなら、先行研究レビューの執筆を最後まで待つ理由は特にありませんし、文章で書き切ってみることで、論理の穴が見つかりやすいからです。論理の穴が見つかったら、そこを埋める先行研究が無いか?という観点で再びレビューに戻り、そこで新たに見つけた研究から、自分が問うべき研究課題がよりブラッシュアップされていくことが期待されます。
まとめ
今回の記事では、質的研究の概要と、研究を進めていく際の全体像を描きました。研究者が明らかにしたいテーマに沿って、適切な分析手法を選んで取り組んでいくことが重要です。
質的研究独特の難しさへの対応や、論文化に当たってどのようにまとめていくのかについては、後編で解説したいと思います。
<参考文献>
- ジョン・W・クレスウェル、ジョアンナ・クレスウェル・バイアス著、廣瀬眞理子訳(2022)質的研究をはじめるための30の基礎スキル おさえておきたい実践の手引き
- 太田裕子(2009). はじめて「質的研究」を「書く」あなたへ―研究計画から論文作成まで― 東京図書
- 佐藤郁也(2002). フィールドワークの技法―問いを育てる、仮説をきたえる 新曜社
- サトウタツヤ・春日英朗・神崎真実 編(2019). ワードマップ 質的研究法マッピング 特徴をつかみ、活用するために 新曜社

この記事を書いた人
本田由美
Yumi Honda
プロフィール
人間関係や悩み・不安、生き方などを専門とする臨床心理学者(公認心理師・臨床心理士)。東京大学文学部(社会学)を卒業後、一般企業で経理・経営企画を担当。その後、東京大学大学院教育学研究科で臨床心理学を専攻して修士号(教育学)を取得しました。現在は、精神科クリニックで心理療法を担当しながら、大学と協働して臨床心理学の研究・論文執筆を行っています(筆頭著者として5本の論文を執筆、ほか共著多数)。心理学・社会学・教育学・経営学・統計学などの知見を活かしながら、これまで500人以上にカウンセリングしてきました。マインドフルネス講師、リラクゼーションセラピストとしても活動しています。