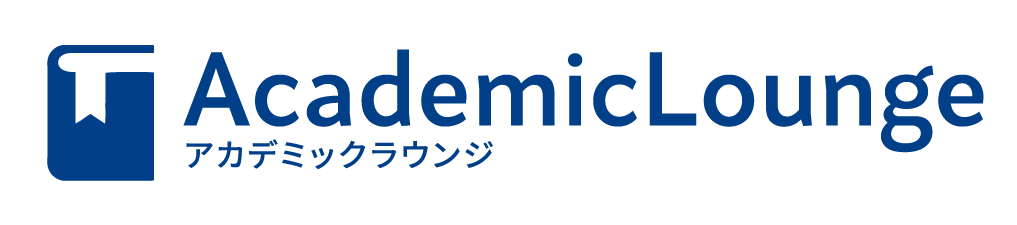質的研究の基本:採択される論文を書くために知っておきたいこと(後編)
前回から今回にかけて、質的研究の解説をしています。前回は、質的研究はどういったものであるのかについて、量的研究と比較しながら述べたうえで、研究を行う際の全体的な流れについて説明しました。
今回は、質的研究で陥りやすい落とし穴(難所)と、その対応について解説します。安易に取り組み始めて、途中で後悔することのないように、しっかりと準備をして取り掛かりましょう。
質的研究で陥りやすい落とし穴(難所)とその対応
(1)リサーチクエスチョンが定まらない
質的研究を行う際には、まず「リサーチクエスチョン」を設定します。リサーチクエスチョンとは、ご自身の研究で明らかにしたい現象(研究の目的)に対して、答えやすいように噛み砕いた言葉で表現したものです。量的研究では仮説を設定することが多いですが、質的研究は探索的な手法なので事前に仮説は設定できず(先入観になってしまいます)、リサーチクエスチョンという形で、何を明らかにするのかを明確にします。
これは架空の研究ですが、例えば、「初級心理職の成長過程を明らかにする」という目的に対して、「初級心理職は、困難に直面したとき、どのように乗り越えるのか」「初級心理職は、どのような学びを経験しているのか」などのリサーチクエスチョンを設定します。
リサーチクエスチョンの設定で悩む場合、その背景には、そもそも研究目的が明確になっていないことが多くあります。大谷(2017)は、質的研究の目的として、以下の5種を挙げました。
- 具体的な状況やプロセスの記述・解明
- 外から見て観察・測定できる行動ではなく、個人や集団の内面的な現実の解明
- 研究対象に潜む問題・課題の探索および発見
- 研究対象に含まれる要素・要因の探索
- 既知の要素・要因間に潜む構造の解明
これらを参考にして、ご自身が明らかにしたいことはどれに該当しそうか、目的を明確化したうえで、その回答を導けるようなリサーチクエスチョンを設定しましょう。
また、リサーチクエスチョンの規準として、「FINERクライテリア」というものがあります(大谷,2019)。
F: Feasible(実施可能性)
I: Interesting(興味深い)
N: Novel(新規・新奇性)
E: Ethical(倫理的)
R: Relevant(必要・必然性)
これらは、研究者レベルの研究計画ではどれも重要な要素となります。FINERクライテリアを意識すると、レベルの高いリサーチクエスチョンを設定することができるでしょう。
(2)分析方法が定まらない
前編で紹介したように、質的研究にはかなり多様な分析方法があります。加えて、各分析方法はそれぞれの認識論や前提に立っているため、前提を理解した上で研究に着手するのは至難の業です。そのため、質的研究の経験がある指導者や同僚が身近にいない場合、新しい分析方法に着手する勇気はなかなか出ないかもしれません。一方で、「周りの人もやっている分析方法だから…」という理由で着手すると、実は自分の研究目的や規模には合致していなかった、ということにもなりかねません。
質的研究法の中から何を選ぶのが適切なのか、判断の一助となるように、ここでは一例としてサトウら(2019)の4象限モデルを紹介します。
サトウら(2019)では、
- 構造と過程(プロセス)のいずれを解き明かすのに長けているか?
- 実存性(実際に存在するもの)と理念性(その背後にある本質的なこと)いずれの理解を目指しているのか?
という2軸で分析法を整理し、以下の4つに分類しました。
「過程×実存性」――モデル構成
「構造×実存性」――記述のコード化
「構造×理念性」――理論構築
「過程×理念性」――記述の意味づけ
それぞれの中でどういった分析法があるのか、分析法の概要はどのようなものかについては、サトウら(2019)の成書をご確認いただければと思います。(なお、この分類自体も試論的にマッピングしたものであり、絶対的なものというわけではないことにご留意ください。)前編の記事では、それぞれに含まれる分析法も紹介しましたので、こちらの記事もご覧ください。
(3)研究協力者が集まらない
リサーチクエスチョンが定まり、分析方法も目途が立ち…しかし、インタビューや観察に協力してくれる方が集まらない!ということもよくあります。卒論や修論のように、締め切りが厳格に定まっている場合、どんどん焦りが募るものです(私自身も経験しました)。
量的研究では、前もって厳密に条件設定してサンプリングします。例えば社会科学系の研究だと、国勢調査のように全数調査を行ったり、対象となる集団(母集団)から、特定の間隔で割り当てしたりします。では、質的研究のサンプリングは、どのように考えると良いのでしょうか?
質的研究におけるサンプリングの方法には、以下のようなものがあります。
理論的サンプリング
グラウンデッド・セオリー・アプローチで用いられる方法で、他の質的研究法でも利用されることがあります。すでに入手したデータの分析結果を踏まえて、まだ明らかになっていない部分や、もう少し詳しく知る必要がある内容を語れるであろう人を、協力者としてリクルートする手法です。
スノーボール(雪だるま式)サンプリング
こちらは、研究に協力してくれた方に、他にも研究の条件に合致する人を紹介してもらう手法です。例えば専門職を対象とした研究だと、同じ領域の人を紹介してもらえるので、確実につながることができるというメリットがあります。
便宜的サンプリング
研究者の身近な人に協力を依頼する方法です。上記2つと比較すると、やや条件設定の厳密さは劣るものの、このようにする以外に手立てがないこともあります。
なお最近では、SNSで研究概要を紹介し、そこに貼られたリンクから応募してもらうスタイルもよく見られます。また、調査会社や単発アルバイトサイトなどを介して、インタビューへ協力できるかを尋ねる方法もあります。スノーボールサンプリングや理論的サンプリングほど、研究対象に合致する人と出会える確率は高くないですが、協力者を募る方法として候補に入れてみるのも一案です。
(4)インタビューが拡散する
さて、やっと協力者も見つかって、いよいよインタビューをする際にも、難しい点がいくつかあります。なお、インタビューは質問の構造度によっていくつかの種類があるのですが、今回は「質問項目はある程度決めているものの、話の流れや重要そうなテーマによって、臨機応変に質問内容を調整する」タイプのインタビューについて扱います。「半構造化面接」や「in depth interview/デプスインタビュー」などが該当します。
インタビューでよくある困りごととしては、意図せずインタビューが拡散してしまうことです。それによって聴きたかった内容をうまく引き出せなかったり、時間がかかりすぎたり…。以下に、散見されるパターンとその対応について記します。
緊張する
ほとんどの場合、研究者と協力者は初対面となります。協力者にとって、初対面の相手にインタビューされるのは、意外と緊張するものです。そのため、急に質問を始めるのではなく、アイスブレイク的な雑談や、お互いに共通する話題などを少し話してから、実際のインタビューに入りましょう。
また、インタビューガイド自体も、最初から深い(熟考する必要がある)内容を尋ねるのではなく、冒頭では比較的答えやすい、事実ベースの話から入り、徐々に気持ちや考えを深掘りできるような構成にします。
話が脱線し、インタビューの目的から外れる
聴きたいテーマがあるにもかかわらず、インタビュー内容が本筋からずれていく、あるいはあまりに詳細に入りすぎて本題が分かりづらくなってくる、ということもあります。もちろん、協力者が快適に話せる状況をしつらえることは大切ですが、コントロールを失った会話はかえってストレスを与えることにもなってしまいます。話を遮ったような印象を与えないように留意しながら、「とても興味深いお話ありがとうございます。私のほうから、また少し質問してもよろしいでしょうか?」など、話題を変える語りかけをしてみましょう。
脱線を警戒した結果、誘導的になってしまう
逆に、脱線しないようにコントロールし過ぎてしまって、誘導的な会話になってしまうこともあります。これでは、研究者の先入観が色濃く出たインタビューとなってしまうため、質的研究として取り組む意味がありません。そのため、先入観を排して、教えていただくという意識を持つことが重要です。
こちらの先入観が強い場合、仮説を確かめるような質問になってしまいがちです。例えば、「専門家の方は、現場に出てすぐの頃はうまくいかないことも多いかと思いますが、そんなときはどうやって乗り越えましたか?」という質問には、うまくいかないという決めつけや、乗り越えるという前提があります。それよりも、「専門家として現場に出てすぐの頃、何か悩むことはありましたか?」と尋ねたうえで、「そういうときはどのように向き合いましたか?」と、順を追って、前提を定めない質問を重ねていきます。
なんだか「いい話」ばかり出てくる
たまにですが、インタビューをしていて、随分かっこいい話や、うまくいった話ばかりが出てくることがあります。しかも、あまり言いよどみなどもなく、スラスラとお答えになる…こういう場合は、もしかすると、研究者の側が相手をそのように導いているのかもしれません。
「教えていただく姿勢、謙虚さが大事」とはお伝えしましたが、「相手をむやみやたらに持ち上げる」のとは違います。相手が専門家だから!と萎縮しすぎてしまうと、協力者は無意識にこちらをガッカリさせないようにと気を張ってしまうものです。そのため、「さすがです!」などあまり持ち上げすぎる(つまり評価する)ことなく、ニュートラルな姿勢で、インフォーマントへの敬意を持って尋ねましょう。
(5)分析が想像以上に大変!
質的研究に取り組む際に、一番大変で、そしてやりがいがあるのが分析だと思います。細かい分析内容や手順は研究法によって異なりますので、ここでは共通する部分についてだけ触れておきます。
まず、データの分量に圧倒されてしまうことが少なくありません。エクセルやワード、あるいは管理ソフトなどを活用して、データを上手に取り扱えるようにします。パソコン上の小さい画面だけで管理すると見落としてしまうこともあるので、個人的には、印刷して全体を眺めたり読み込んだりすることをお勧めします。
分析にあたっては、「分析的枠組み(概念的・理論的枠組み)」に基づいた分析を行うことが推奨されています。分析的枠組みとは、先行研究の知見に基づいて設定される、データ分析の基盤となるものです。分析的枠組みを参照することで、恣意性が抑制される、読者が結果を理解しやすくなる、先行研究の積み上げの中に自分の研究を位置づけやすくなる、などのメリットがあります(大谷,2019)。一方で、分析的枠組みに過度に依存することで「理論ありき」の分析になってしまって、データの奥にある意味を見逃す可能性があるという警鐘もあります(Sale&Carlin,2025)。そのため、あくまで「枠組み」であることを理解しながら、その枠組みに縛られずに柔軟な分析を心がける必要があります。
また、分析をしながら疑問に感じたことや、先行研究を調べる必要がある点など、随時メモをしていきましょう。分析法によっては、そのようにメモを記述すること自体も定型化されていますが、そうでない場合でも、分析を深めるためにメモを活用することをお勧めします。
(6)結果図:内容を適切に表現できているか
全ての質的研究の論文で結果図を作成するとは限りませんが、多くの場合、分析の結果を視覚的に理解できる図を作成します。自分では分かりやすい図になったと思っていても、人から見るとよく分からない図、ということは往々にしてありますので、丁寧な作図を心がけましょう。
例えば、以下のような点に留意します。
- 凡例を必ず付ける
- 矢印の始点と終点を、それぞれ一意の場所に配置する(項目と項目の間など、どこを指しているのか分かりづらい矢印に注意)
- 濃淡や斜線、破線などを使って、白黒印刷でも見やすくする(たまに、白黒印刷になるはずの図をカラーで作成する方がいますが、カラーを白黒印刷にすると色がつぶれて、かなり不明瞭な図になります)
- ストーリーラインなど「文章」でも結果を記述する場合、文章の流れと図中の項目の位置を対応させる
可能であれば、協力者や指導者、同僚などからも図に関するコメントをもらいましょう。
(7)分析結果と考察の記述
分析結果を記述するにあたり、まず、結果と考察の考え方を紹介します。量的研究の場合は「結果」と「考察」が明瞭に分かれるものですが、質的研究においては、結果自体に研究者の考察も含まれているとの考えから、「結果と考察」といった書き方になることもあります。ただし、この辺りは研究者や投稿先によっても考え方が変わるので、投稿先に掲載されている論文を参考にすると良いと思います。
余談ですが、結果の記述方法に関してもいろいろな意見があります。例えば、質的研究でよく見られる、「分析の結果、●個のカテゴリーが抽出“された”」という表現について、「研究者の視点をもって行なった分析なのだから、抽出“した”とすべきである」との声があります。そのため、記述の方法については、自分なりにできるだけ誠実に書き、細かい方針に関しては査読者からのコメントに応じていく…と割り切るのも一つの考え方です。
また、質的研究の結果は、丁寧な記述が求められるものの、ともすると「ダラダラ書いている」ように見えてしまう危険性もあります。そうならないためにも、時間をおいて何度も読み返し、添削・校正を重ねましょう。
なお、前編でもお伝えしたように、協力者の募集、データ収集、分析、執筆は一直線に進むものではなく、行きつ戻りつする性質のものです。いったん書いて添削し、疑問を感じたらまたデータに戻って分析しなおしたり、新たな協力者を募集したりします。
(8)どこに投稿するのか
質的論文を投稿する場合に問題となってくるのが、「査読者および編集者、ひいては投稿先の学術雑誌そのものが、質的研究にどのような態度を取っているのか」です。質的研究は比較的新しい研究であることから、査読者が学生のときに質的研究を学んでいないこともありますし、一部の研究者が「量的研究こそが科学的な研究であって、質的研究は妥当性を欠く」という考えを持っている様子もいまだに見受けられます。
そのため、投稿先の選定にあたっては、その雑誌のバックナンバーを見て、質的研究が掲載されているかを事前に確認することも大切です。査読者からの質問や意見に対して、質的研究の説明も含めて回答するとなると、多大な労力がかかってしまうためです。
一方、学会発表に関しては、さまざまな研究者と交流するため、あまり質的研究が取り扱われていない学会でも積極的に発表すれば良いと思います。ご自身の研究が他者の目にどのように映るのか、どのような点で疑問を持たれるのか、口頭で情報交換しながら探索してみてください。
まとめ
前回、そして今回と、先行研究や実体験に基づきながら、質的研究の特徴と難所について解説しました。質的研究の醍醐味は、日常実践の中で抱いた疑問や問題意識について探求し、そこで明らかになった結果を日常実践に還元し、さらに研究へとつなげていく…というところにあります。大変だけどやりがいのある質的研究に、ぜひ取り組んでみていただけたら幸いです。
<参考文献>
- 大谷尚(2017)質的研究とは何か, YAKUGAKU ZASSHI, 2017, 137 巻, 6 号, p. 653-658,
- 大谷尚(2019)質的研究の考え方―研究方法論からSCATによる分析まで 名古屋大学出版会
- Sale, J.E., Carlin, L. (2025) The reliance on conceptual frameworks in qualitative research – a way forward. BMC Med Res Methodol 25, 36 https://doi.org/10.1186/s12874-025-02461-0
- サトウタツヤ・春日英朗・神崎真実 編(2019) ワードマップ 質的研究法マッピング 特徴をつかみ、活用するために 新曜社

この記事を書いた人
本田由美
Yumi Honda
プロフィール
人間関係や悩み・不安、生き方などを専門とする臨床心理学者(公認心理師・臨床心理士)。東京大学文学部(社会学)を卒業後、一般企業で経理・経営企画を担当。その後、東京大学大学院教育学研究科で臨床心理学を専攻して修士号(教育学)を取得しました。現在は、精神科クリニックで心理療法を担当しながら、大学と協働して臨床心理学の研究・論文執筆を行っています(筆頭著者として5本の論文を執筆、ほか共著多数)。心理学・社会学・教育学・経営学・統計学などの知見を活かしながら、これまで500人以上にカウンセリングしてきました。マインドフルネス講師、リラクゼーションセラピストとしても活動しています。